COLUMN
コラム

木の箱に入れられたマウスが教えてくれること
――1987年・静岡大学の実験から考える住まいの材質
住宅の広告やパンフレットを眺めていると、
「木の家は健康にいい」「自然素材は体にやさしい」といった
フレーズを目にすることがありますよね。
とはいえ、それが単なるイメージ戦略なのか、実際に根拠があるのかは
気になるところではないでしょうか。そんな中でしばしば引用されるのが、
1987年に静岡大学で行われた、マウスを使った居住材質の比較実験です。
実験の概要
静岡大学農学部の研究グループは、
マウスを「木製」「コンクリート製」「金属製」のケージ
(木の箱やコンクリートブロック、金属製の飼育箱)で飼育しました。
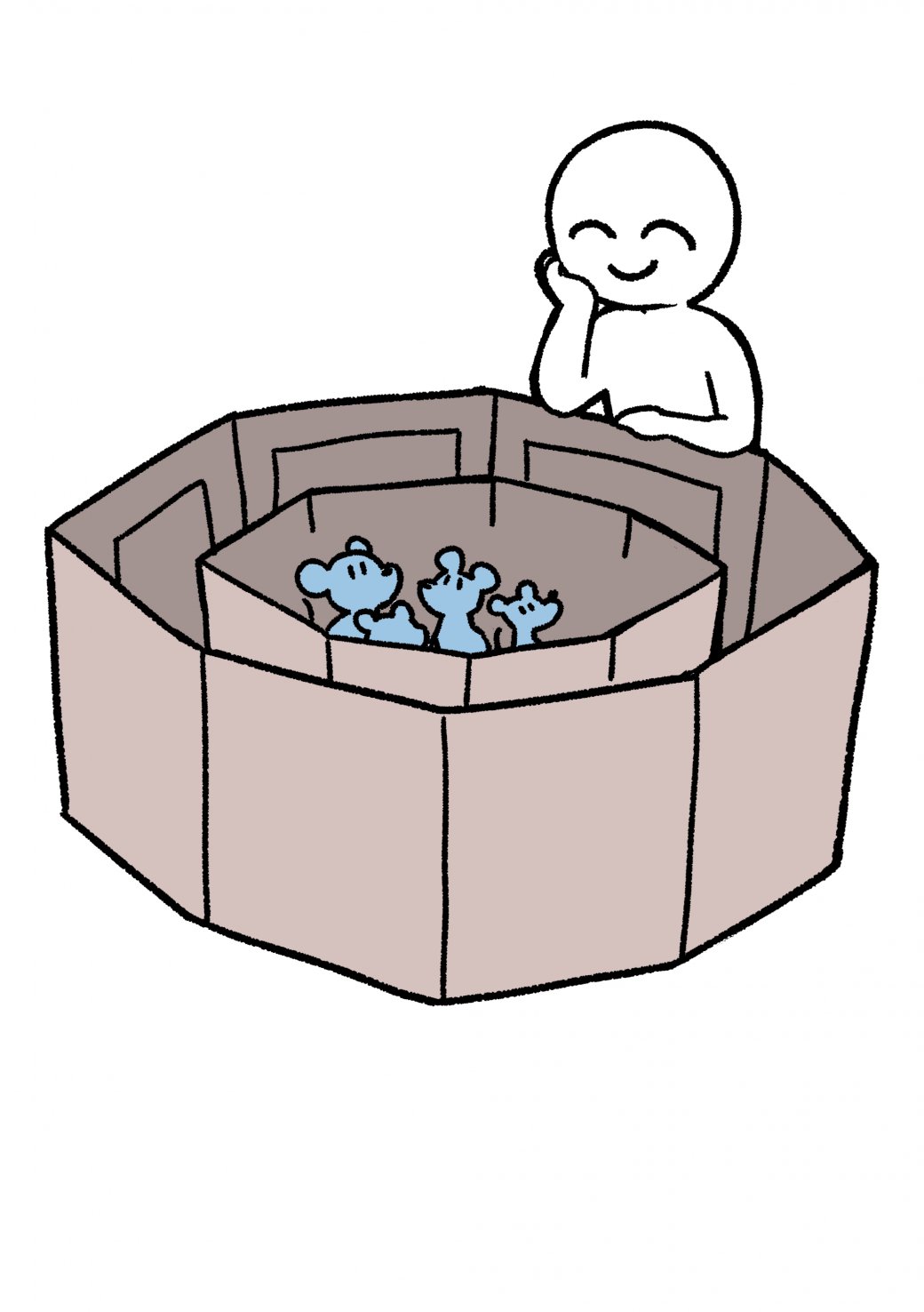
比較されたのは、マウスの成長、体重増加、臓器の発達、
そして特に注目されたのは「第2世代の仔マウスの生存率」です。
結果は驚くほどの差が出ました。生後23日齢での生存率は、
-
木製ケージ:約90%
-
金属製ケージ:約40%
-
コンクリート製ケージ:約10%
ほぼ同じ条件下にもかかわらず、材質によって仔マウスの命の明暗が分かれたのです。
研究者の考察
なぜこんな差が生まれたのか。
研究者が注目したのは「熱伝導率」でした。
マウスの新生仔は毛が生えそろっておらず、自分で体温を調整する力も
弱い存在です。そのため、床材や壁材に触れるだけで熱を奪われ、
低体温に陥りやすいという特徴があります。
-
木材は熱を伝えにくく(熱伝導率が低い)、接触しても体温が逃げにくい。
-
コンクリートや金属は熱を奪いやすく、マウスにとって過酷な環境になることがある。
つまり、木のケージはマウスにとって「ぬくもりを奪わない箱」であり、
そのことが生存率の高さに直結した、というのが実験から導かれた結論でした。
「木の家=健康住宅」なのか?

この実験は住宅業界でしばしば取り上げられ、
「だから木の家は健康にいい」と紹介されることがあります。
確かにインパクトのある数字ですし、説得力も感じられます。
しかし多角的視点が必要です。なぜなら――
-
マウスと人間は違うから
マウスは体が小さく、被毛が未発達な仔は特に熱の出入りに敏感です。
一方、人間は衣服を着て、暖房器具を使い、断熱材に守られた空間で
生活します。単純に「木だから健康」「コンクリートだから不健康」
と結論づけることはできません。
-
実験条件がフェアではないところがある
温度や湿度、換気などの環境要因は完全に制御されていたわけでは
ありません。木製ケージは多少の吸湿作用があり、内部の環境が
安定しやすかった可能性も考えられます。
-
何度同じことをしても同じような数字に帰着するのか
この研究は今でも紹介されますが、国際的に繰り返し検証され、
学会で広く引用されるようなデータにはなっていません。
つまり、「木材はいいらしい」という一例として受け止めるのが妥当です。
それでも残る示唆
それでもこの実験が示しているのは、
「私たちが見て・触れている素材が体に影響する」という事実です。
冷たい床材は冬場に足先から熱を奪い、子どもや高齢者にとっては
体調の不調につながることがあります。一方で、木のフローリングに
素足で立ったときに感じるぬくもりは、単なる感覚的な心地よさ
だけでなく、実際に熱の伝わり方が異なるために生じている現象です。
この「触れて心地よい」という感覚は、マウスにとって生死を分けるほど
強烈に作用しました。人間にとっても、長い時間で「快適感」や「健康感」
を左右する要素であることは間違いないでしょう。
住まいにどう生かすか

結局のところ、私たちがこの実験から学べるのは
「住まいの材質はただの見た目やイメージだけではない」という点です。
-
小さな子どもがハイハイする床が冷たいタイルか、柔らかい木か。
-
高齢者が素足で過ごす冬の居間が、どんな質感で作られているか。
-
夏や冬の室温管理において、素材がどう体感に影響するか。
木だから絶対に健康、という単純な話ではなく、
少なくとも「暮らす人の体にどう触れるか」という視点で
材質を選ぶことは、家づくりにおいて大切なポイントになりそうです。
おわりに

1987年、木の箱に入れられたマウスたちの実験は、
単なる学術的なデータにとどまらず、
「住まいの素材が生き物にどんな影響を与えるか」を考えさせてくれます。
人間はマウスよりずっと賢く、工夫する力も持っています。
それでも「触れる素材が心地いい」「木のぬくもりが安心感をくれる」
という感覚は、科学的にも裏付けられる部分があるのです。
家を選ぶとき、図面や価格だけではなく
「自分や家族の体がどんな素材に触れて暮らすのか」という視点を持つ――
それが、この実験が現代の私たちに残してくれた
暮らしのヒントではないでしょうか。




